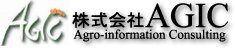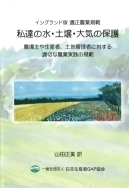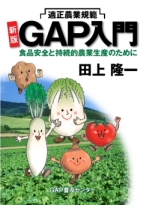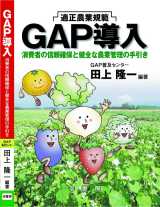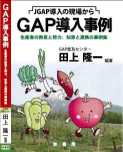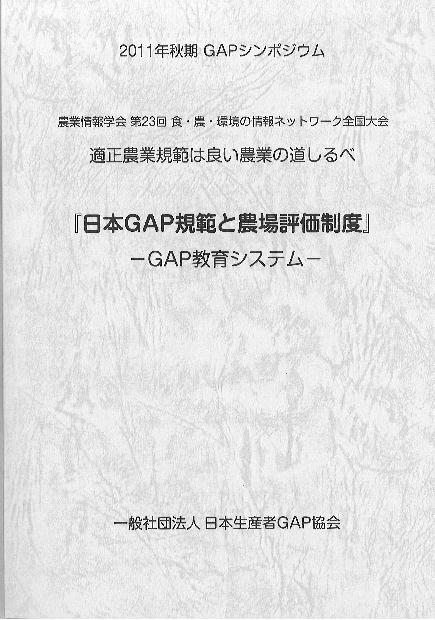年頭のご挨拶
「持続可能性と食品安全は21世紀農業の世界共通課題」
株式会社AGIC
代表取締役 田上隆一
平成27年の新春のお慶びを申し上げます。
今から10年前の2005年2月8・9日に、明治神宮外苑にある日本青年館ホテルに、全国から農業生産や農産物取扱いの関係者823名を集めて、日本で始めてとなる「GAPシンポジウム」を開催しました。メインテーマは「食の安全性確保と適正農業規範」であり、発表・討論の内容は2つでした。一つはGAP規範による農場認証の事実上の国際標準規格であるGLOBALG.A.P.(当時の名称はEUREPGAP)認証取得について、もう一つは農業生産管理や農産物流通管理、特に農薬管理やトレーサビリティのICT(当時の表現はIT)活用についてでした。
このシンポジウムの開催は、農業情報学会が中心になり、国や企業に働きかけて大きな関心を呼び、その後の日本の農業振興や農政、GAPの普及に大きな影響を与えることとな りました。
「ICT」や「GAP」といえば、現在でも日本の農業政策上の重要なキーワードです。 昨年、農業情報学会では、農業・農村のイノベーションとサステナビリティをテーマにし た書籍「スマート農業」を農林統計出版から刊行しました。今やスマートフォンなどの形で、ICTは飛躍的な進歩を遂げ、人々の暮らしを変え、仕事の内容を変え、ビジネススタ イルをも変えました。農業も例外では在りません。
一方のGAPは、日本では、世界を意識しないで「J:Japan」にこだわる独自の取組みを してきたために大きな進展が見られていません。食料がグローバルマーケットであるにも かかわらず、GAP基準が国際標準でなければ、日本農業が攻めに転じることができないば かりか、大量に輸入される農畜産物から日本農業を守ることもできなくなります。
これらは水産業でも同様であり、世界の巨大食品企業ではバイングパワーを発揮して、 「世界基準での持続可能性への取組みが無ければ取引を止める」といって、一国の水産業が「経営危機に至っている」という事態にもなっているほどです。
GAPの目的であるサステナビリティ(持続可能性)とフードセーフティ(食品安全)へ の取組みは、21世紀農業の世界共通の課題です。
ASEAN経済共同体は、今年(2015年)の末にも実現される見通しです。日本からインド ネシアに輸出を計画していた静岡県のクラウンメロンは、昨年、相手先からGLOBALG.A.P.認証を要求されて認証を取得しました。
例え「嫌いだ」としても、逃れることができないグローバリゼーションです。国際化・標準化を現実の問題として受け止めて対応し、その上で日本の特質を発揮していくことが日本の農畜水産業に求められています。
私どもが民間で本格的なGAPの推進活動を開始し、国際標準GAP規格の必要性をうったえ てから10年。今、農業政策においても、地域の農業振興策においても、その具体的な取組みが始まっています。
株式会社AGICは、一般社団法人日本生産者GAP協会とともに、主体的に取り組む産地と生産者を応援します。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
(GAP普及ニュース41号,年頭のご挨拶から)